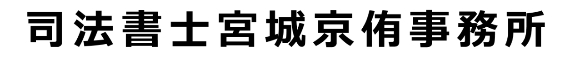概要

相続放棄に必要な戸籍の収集や相続放棄申述書の作成を代行いたします。照会書への回答作成もサポートいたします。
| 料金(総額) | 登録免許税 |
|---|---|
| 21,000円~ | – |
| オンライン見積 | 対応エリア |
| 無 | 鳥取県西部 |
依頼を決めた人も、依頼しようか迷っている人も、まずは無料相談を予約してね♪
相続放棄の基本的な法律効果等の確認
以下に相続放棄の基本的な法律効果等を記載しましたので、ご確認ください。当該法律効果等を確認したうえで、なお相続放棄の意思があるのであれば、引き続き当ページをご覧ください。- 相続放棄は各相続人ごとにおこなう
相続放棄は各相続人ごとにおこなう必要があります。例えば、亡くなった方がA、相続人がB及びCの場合、B及びCが相続放棄をするには、B及びCがそれぞれ相続放棄をする必要があります。 - 亡くなった方の権利義務を一切承継しなくなる
相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産だけではなく、不動産等のプラスの財産も承継されなくなります。また、財産の一部のみの相続放棄はすることができません。 - 相続税の支払い義務が原則なくなる
相続放棄をすると、相続税の支払い義務が原則なくなりますが、生命保険金や死亡退職金を受け取ると当該受取金に相続税が課税される可能性があります。(注1、2)
ご依頼条件
弊事務所にご依頼される場合、次の3つの条件を全て満たす必要があります。- 反社会的勢力ではないこと
- 自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内であること
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認に協力してくれること
弊事務所にご依頼された場合の流れ
弊事務所にご依頼された場合は、おおむね次のような流れで業務を遂行してまいります。- 電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約いただきます。
- ご予約いただいた相談日に次のようなことをおこないます。(注1) ・亡くなった方の相続関係の聞き取りをし、暫定的な法定相続人の確認 ・必要書類の収集方法(司法書士が収集するのか依頼者ご自身で収集するのか)の確認 ・おおよその見積額の提示及び報酬体系の説明 ・今後の流れについての説明 など
- 弊事務所より、案内書類を郵送いたします。
- 郵送された案内書類にしたがい、「委任状への署名捺印」などをおこなっていただきます。
- 「収集していただいた証明書」や「署名捺印していただいた委任状」などを返送用封筒に入れて弊事務所へ郵送していただきます。
- 委任状を含めた全ての必要書類がそろいましたら、家庭裁判所に相続放棄申述の申立をいたします。なお、収集していただいた証明書に不足があった場合は、弊事務所が不足分の証明書を取得(1件あたり1,000円の司法書士報酬と実費が発生)いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 請求書をお渡し(郵送又は弊事務所でのお渡し)いたします。
- 請求書記載の請求額をお支払いいただきます。お支払いの確認後、領収証を発行いたします。(注2)
- 相続放棄申述の申立から約1週間後に、家庭裁判所から照会書という書類が送られてきますので、当該照会書に回答したうえで家庭裁判所に返送してください。なお、照会書への回答の仕方がわからない場合は、無料でサポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。(注3)
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、相続放棄の手続きは完了となります。
必要書類
「司法書士費用を可能な限り抑えたい」という方のために、「できるだけ依頼者ご自身で各証明書を収集し、不足する証明書の収集のみを弊事務所に依頼する」というかたちにも対応いたします。相続放棄申述の申立には、次の書類が必要となります。なお、ご依頼内容によっては追加で必要となる書類がでてきますので、そのような場合は相談等でご説明させていただきます。
-
亡くなった方の配偶者又は子が相続放棄をする場合
- 亡くなった方の死亡の記載がある作成後3か月以内の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注)
- 亡くなった方について次のいずれかの書類 ・作成後3か月以内の住民票の除票 ・作成後3か月以内の戸籍(除籍)の附票
- 相続放棄をする相続人の作成後3か月以内の戸籍謄本(注)
-
亡くなった方の父母が相続放棄をする場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの作成後3か月以内の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注)
- 亡くなった方について次のいずれかの書類 ・作成後3か月以内の住民票の除票 ・作成後3か月以内の戸籍(除籍)の附票
- 相続放棄をする相続人の作成後3か月以内の戸籍謄本(注)
-
亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
- 亡くなった方の出生から死亡までの作成後3か月以内の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1、2)
- 亡くなった方の父母の死亡の記載のある作成後3か月以内の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本(注1)
- 亡くなった方について次のいずれかの書類 ・作成後3か月以内の住民票の除票 ・作成後3か月以内の戸籍(除籍)の附票
- 相続放棄をする相続人の作成後3か月以内の戸籍謄本(注2)
料金
お支払いいただく金額及びその内訳
内訳 | 金額(総額) |
|---|---|
①基本報酬 | 21,000円 |
②証明書収集 | 1,000円×証明書収集件数(注) |
合計 | ①+②+実費 |
実費について
次の実費をお支払いいただきます。- 家庭裁判所への手数料
- 証明書の収集を弊事務所にご依頼された場合は次の実費 ・証明書の発行手数料 ・証明書を郵送請求した場合の郵便料金 ・証明書を郵送請求した場合の定額小為替の発行手数料
上記の実費以外の実費を請求することはないから安心してね♪
無料相談の予約
次のバナーより、電話(0859-46-0602)又はネットにて無料相談の日時をご予約ください。予約まっているぞ!!
よくある質問
- 本人確認書類の提示はどのようにしておこなうのですか?
-
次のいずれかの方法によって、本人確認書類をご提示(ご提出)していただきます。
・相談の際に本人確認書類をご提示 ・弊事務所から郵送されれる「本人確認等のご案内」に従って、本人確認書類のコピーをご提出
- 相談にかかる時間と相談回数はどのくらいですか?
- 相談にかかる時間は30分から1時間です。相談回数は1回ですむことがほとんどですが、場合によっては複数回になることがあります。